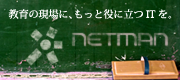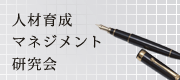発明家。1966年静岡県沼津市生まれ。
東芝テック、日本ユニシスを経て、1999年4月株式会社ネットマンを設立。
学校や企業の教育において、ITを活用した「学び合う場作り」を提供する。
教育現場での「ケータイ活用授業」のパイオニア。
人材育成に必要なITを開発、特許を取得するなど、「教育IT発明家」として知られる。
キャリア開発の人材育成プログラムを開発、三菱東京UFJ銀行や日立グループ、旭化成グループ、明治大学、駒澤大学、高知大学などで自ら講師を実践する。
NPO人材育成マネジメント研究会の理事長も努め、「人材育成の質の向上」のため、 多くの勉強会を実践する。
また、住んでいる伊豆の地域活性にも力をいれ、 JAXAの協力を得て小学生向けの親子で行う工作の実験教室 「伊豆・宇宙の学校」を主催している。
学習コミュニティーのネットワーク「知恵組」代表
関連サイト
株式会社ネットマン http://netman.co.jp
NPO人材育成マネジメント研究会 http://hrdm.jp
知恵組 http://chiegumi.jp
伊豆・宇宙の学校 http://uchu.i-ra.jp
東芝テック、日本ユニシスを経て、1999年4月株式会社ネットマンを設立。
学校や企業の教育において、ITを活用した「学び合う場作り」を提供する。
教育現場での「ケータイ活用授業」のパイオニア。
人材育成に必要なITを開発、特許を取得するなど、「教育IT発明家」として知られる。
キャリア開発の人材育成プログラムを開発、三菱東京UFJ銀行や日立グループ、旭化成グループ、明治大学、駒澤大学、高知大学などで自ら講師を実践する。
NPO人材育成マネジメント研究会の理事長も努め、「人材育成の質の向上」のため、 多くの勉強会を実践する。
また、住んでいる伊豆の地域活性にも力をいれ、 JAXAの協力を得て小学生向けの親子で行う工作の実験教室 「伊豆・宇宙の学校」を主催している。
学習コミュニティーのネットワーク「知恵組」代表
関連サイト
株式会社ネットマン http://netman.co.jp
NPO人材育成マネジメント研究会 http://hrdm.jp
知恵組 http://chiegumi.jp
伊豆・宇宙の学校 http://uchu.i-ra.jp
- 発明家への軌跡と永谷のキャリアに関する歴史
-
今だからこそ人に語れる、恥ずかしくも、誇らしくもある私の歴史です。
これからの社会を担う世代へ、何かの参考になればと思い、私の歩んできた道、葛藤、苦しさ、喜びを「自己開示」して、ここに綴ります。
そしてこれは、40歳を過ぎた今だから書けるんだと思います。
いつでも、そのときはそのときなりに一生懸命だっただけなんだと思います。
■生徒時代
小学校2年のときに言いました。
『将来発明家になりたい』
きっかけは、”池の中覗き器”でした。
学校の中庭にあった池の中で泳ぐフナを観察したかった私は、
ジュースの缶のフタと底くり貫き5個ほどつなげ望遠鏡のような形を作り、先に豆電球をつけ、直列でつないだ単一の電池と細い電線でつないで作りました。
この”池の中覗き器”が発明工夫展で賞をもらったことがきっかけで、発明家になりたいと思ったのでしょう。
夜釣りが好きだった父親の道具箱にあった電球と大量の電池。電池を何個もつなげるとより明るく光るのが楽しくて遊んでいただけ。今から考えると単なる手作りオモチャですが、それがその後の私の人生を決定付けるとは思っても見ませんでした。
ラジコンカーが好きでした。友達よりも早く走らせたいために、モーターを分解し、コイルを巻きなおし、磁石と内枠の間に新聞紙を挟み、コイルとの距離を縮め、スーパーモーターを手作りました。自分のラジコンカーがビューっと高速で走ったときはなんともうれしかったものです。
小5になると、ハム無線の試験を受けたくなり、問題集買いました。理由は、近所のおじさんの部屋に無線の機械がたくさんおいてあり、「CQ,CQこちら・・」と交信するおじさんが”かっこいいな~。”と思ったからです。何回も何回も国家試験の問題集をやるものですから、試験問題を暗記してしまいました。抵抗と電流と電圧の問題がでたら、電圧だったら掛ければよく、電流だったら割ればよいと勝手にあみ出しました。中学に入ってオームの法則を教わったときは、えっ?もっと早く教えてもらえば、楽だったのに。と思ったのを覚えています。
そんな理科好き少年は、勉強でも、数学と物理は大得意。いい大学に入り、将来研究者になるんだ。と思っていました。高校では具体的に”半導体の技術者になって、つくばにある研究所で働きたい”と夢を思い描いていました。
そんな夢は、たった一回の失敗で絶たれました。
共通一次試験(現:センター試験)の一日目の数学Ⅰ。当然200点満点を楽勝でとることを想定していた私は、ルート2の2乗がとけず、108点しか取れなかったのです。
ルート2を何桁まで覚えられるか競争していた私はなんと20桁をひたすら掛けていたのです。馬鹿ですよね。時計を見ると時間がかなり進んでしまっていた。『あっ200取れない。』って思った瞬間から記憶がないんです。ようはテンパッたってことですね。
この煩悩の数字108.毎年年末になるとみんなが鐘をつく。。私は毎年大晦日にこの悪夢を思い出すことになるのです。
以降心の奥では、劣等感のカタマリで生きていかねばならない人生となったわけです。
■学生時代
浪人したくなかった私は、国立2次試験の練習用にと受けていた私立大学に行くことになりました。もちろん早く親元から離れ東京に行きたかったのでワクワクしていたと思います。
(国立は上、私立は下という誤った考えで受験していた時点で世間知らずです)
大学の勉強も1年の最初の英語の授業で見切ってしまいました。
なんで、このレベルのことを大学に入ってまでやらねばならんの?
うちの高校なら最低クラスでもこのレベルでないわ。
と心の中で叫びました。
(最初の授業ですから当然です。勘違いの甘ったれチャンです。)
勉強がやる気のないこの甘ったれちゃんは、見事留年するのです。
将来半導体の研究者になりたい。自分の力で、世界初のチップを作ってやるぞ。と夢を描いていた成績優秀の青年がたった1年で底まで転落するのです。
それを救ってくれたのは友人でした。
クラスで声をかけた何人かとつくったロックバンド、SAITEI-BAND
1年で工学部サッカー部を退部した自分を迎えてくれたサッカーサークル、Arce
この2つの居場所によって、今でも付き合う一生の友と出会うことができたのです。
柔軟性にかけ、視野が狭かった私は、この友人たちとの行ったいろんな事柄によって社会で生きていく基礎的な力をつけていったのです。
社会が敵であった自分から、社会の中の一員となったのです。
(ちなみに3年からは主に”生産管理”を大いに勉強しました。統計学やオペレーションズリサーチ(OR)など、その後の仕事に大いに役立つスキルを大学で身につけたのでした。)
■サラリーマン時代
就職活動を始めようとしたとき、なんとなく”システムエンジニア”という職業に憧れをもちました。物理少年は、コンピュータを使ったシステムに興味をもったのです。そして30歳になったら自分の会社を作ろうと決めていました。そんな中、最初の会社東京電気(現:東芝テック)に入りました。2年間工場でPOSレジの品質保証部門で働きました。POSレジとは、コンビニエンスストアにあるレジのことです。
ハードウェアの耐久試験や品質に問題があると生産技術と製造ラインの間に立ち、製品の品質を上げる仕事をしました。
ここで製造工場のイロハを身につけることができました。
システムエンジニアになりたかった2年後25歳で、日本ユニシスに転職するのです。
この会社には33歳まで8年在籍しましたが、それはそれは必死に良く働きました。製造システム部門に配属され、大手企業の工場の生産管理システムの開発を行っていました。自分の考えたシステムで、製造指示が行われ、大きな工場が動くのですから責任重大です。MRPなど知識がまったくないのに任せられるのですから、朝から終電まで働くのは当たり前で、空いた時間にも必死に勉強をしました。数年後には、生産管理システムなら俺に任せろと会社で言えるようになったのでした。
システムもお客様のいいなりで作ったわけでは在りません。ニーズも取り入れながら自分として理想の工場とはこういうものだ。利益を上げる工場はこういうものだ。中間在庫の取り扱いはこうすべきだという意見を積極的に工場長や生産管理部の方々に提言したものです。今から考えたら、かなり生意気ですね。よくもまあ素人の20代の若者の提案にお客様も耳を傾けてくれたものだと感謝しています。
壁にも多くぶつかりました。でも会社の上司は助けてくれた記憶がありません。
どうしてもとある設計ができないテーマがあり上司に相談に言っても、
「んー永谷。頭から煙が出てないぞ。もっと考えろ」
といって突き放されるだけ。
自分がなんとかするしかないんだと、奮い立ったものです。
頼りない私を育成してくれたのは、この会社の厳しい環境だったのです。
(後から聞いた話ですが、会社の上層部は『永谷は自由にやらせたほうがいい仕事するから、細かいこと言うな』と話していたそうです。なんとも暖かい話です)
33歳になったとき次年度から部下ができるのは明白でした。仕事はとても楽しくチャレンジさせてもらっていたので続けるか悩みましたが、大学を出たときに決めた自立の道を選ぶことにしました。部下がいる立場になったら勝手に辞められないだろうと思ったからです。
■ネットマン時代
1999年4月 ネットマン社を設立しました。
設立当初から、次から次へと新しいソフトウェア商品やサービスを開発しました。
一時は、社員7人で13個の商品というときもあったくらいです。早すぎて市場に受け入れられないこともあり、またシステムエンジニア出身の私に営業マンを育てる力量がなく、売り上げにはいつも苦慮していました。
それでもソフトウェアはいつも先駆的なものを開発していました。たとえば、教育にケータイを活用するITシステムは2001年から発売しました。
(でも当時はケータイ禁止。売れるはずありません。今は時代が変わり、たいへん着目されています)
そんな中、2005年12月出願した、”行動改善システム”が特許をとることに成功したのです。この商品の画期的なところはわかってはいましたが、過去なんどもチャレンジしても取れなかった特許がやっととれたという印象でした。
弁理士の先生から送られてきた”特許証”を見るまでは、「あっやっととれたのね」くらいの印象でした。
ところが、初めて”特許証”を見たとき、足の先がぶるぶる震え涙が止まらない状況になったのです。そこにはこんなことが書かれていました。
--------------
発明の名称:行動改善システム
発明者(Inovater) 永谷研一
---------------
ふっと静かに 「あっ夢が叶った。。」 と思いました。その後は、走馬灯のように
小学校2年生ときの”発明家になりたい”と思ったこと。
18歳で、受験で挫折したこと。
20代でシステムエンジニアで必死に働いたこと。
30代で会社を切り盛りしてなんとか生き抜いたこと。
よくよく考えてみたら、サラリーマン時代もいつも独自のアイデアで仕事をしていました。上司に直談判して、やらせてもらったり、時には営業の考えに反して自分の考えを通したり、お客様のためにベストと思うやり方をしてきました。
また会社を作ったあとも、独自の商品を何個も開発してきました。
そういえば大学時代もオリジナルソングと題していつも自分たちの音楽を作っていたのです。
そうです。私はまったく道を外していなかったのです。むしろまっすぐに自分の”ありたい姿”に向かって人生を走ってきたのです。
18歳で受験を失敗したことをいつまでも心の傷として生きてきました。
社会的に大きな仕事をやってのける人をみて、「なんで俺じゃないの?」と恨んだこともありました。
でも違ったのです。私は、小学校2年生のときに思ったとおりの生き方をしてきたのです。
「発明家になりたい」というのは
「自分のアイデアで新しいものを作って、みんなを喜ばせたい」
と思っていたのです。
それに気づかせてくれた”特許証”は僕の宝物になったのです。
自分のすべてを許せた瞬間だったのです。
「あー僕は僕でいいんだ。このまま、まっすぐ歩んでいこう」
そう思った40歳の夏でした。
今では、ITシステムを活用した教育改革にまい進する幸せな日々をおくらせてもらっているんです。
■終わりに。
とある大学の先生がおっしゃってくれました。
「永谷君は大学受験に成功していたら、つまんない男だっただろうねえ。」
とあるNPOの代表も言ってくれました。
「劣等感がパワーになることもあるんだよ。それを受けとめ大切にしなさい。」と。
本当そうです。ありがたい言葉です。
自分におきたすべてのことに感謝します。
ありがとう。