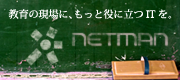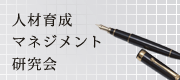2011/02/19 (土)
2011/02/19 (土)
金城大学短期大学部「保育人材養成に係る「特化教育」の展開活動報告、交流研究会」
2011年2月19日(土)
石川県白山市松任文化会館において、金城大学短期大学部の教育GPの成果発表として
「保育人材養成に係る「特化教育」の展開活動報告、交流研究会」が行われ、
参加してきました。
私は最近、奈良の大学のキャリア教育の外部評価委員になっている関係や
静岡の大学で保育人材養成のeポートフォリオを開発している関係で、
幼稚園・保育園・小学校の教員養成に深く関わっているからです。
1.挨拶:中山治男学長
2.基調講演:福島大の大宮先生
3.特化教育:和泉先生の説明
4.研究交流:東海短大の山本先生、桑原先生の発表
5.シンポジウム1:特化教育を体験した学生たちのプレゼン
6.シンポジウム2:受け入れ園の主任先生たちのパネルディスカッション
金城大学短期大学部の教育成果が良く分かるすばらしいシンポジウムでした。
基調講演での福島大学の大宮勇雄先生の話には大変共感しました。
「こどもを否定的に見すぎていないか。もっと肯定的に見よう」
「こどもを希望ある可能性が高い豊かな人として見よう」
「"意欲"を育てる。安心と熱中が大切」
「"意欲"とは、困難に粘り強く立ち向かおうする態度である」
「大人が見方を変えれば、こどもの意欲は育つ」
確かに私たちはこどもの本当の成長を見ていないのかもしれません。結果思考に走りすぎ、何が"できる"何が"できない"ということにこだわり過ぎていると思いました。
先生の「人より早く計算ができるようになったからってその子が将来よくなると
いう保障はどこにもない」という言葉に大いなる気づきと共感を得たものです。
本当に"人"を大切にするということは、その人自身を尊重することに他ならないんだなと感じました。
シンポジウム1での学生たちのプレゼンは大いなる感動を覚えました。
「乳児保育」
「障害児保育」
「音楽」
「美術」
の4分野に分かれて、特色ある教育を行ってきた事例を発表されたのです。
学生たちの試みは最初戸惑いながらもこどもたちと真剣に向き合い自分たちで考えて
行動していった軌跡です。
こどもたちの一人ひとりを真剣に見つめる学生たちのまなざしと態度と行動が
特化教育を通じて養成されていっているのがよく分かりました。
まさに和泉先生の説明にあった「いま・ここを大切にする保育」の実践です。
リカレント(現職教育者を招いての授業)教育も効果的と感じました。
また親御さんとの関係を重視している発表が多かったのにも気づきを得ました。
一方的になることなく保育者と保護者が一体となって進めていく保育の姿です。
このような教育を受けた学生たちが先生になっていく幼稚園・保育園にこどもを
預ける親御さんは安心で心強いだろうなと感じたところです。
また昼休みを通じて、パネルセッションを学生自身が行っていました。
このような発表を通じて自分たちが何を学んできたのかの振り返りになり、
また資料などアウトプットを作ることを通じて実績を皆に知らせることができます。
とてもよい教育手法だなと思います。
学生たちも気軽に声をかけてくれ、堂々と自分たちのしてきたことを説明している
姿を頼もしく感じました。
最後のシンポジウム2での受け入れ側の幼稚園・保育園の先生方の話はとても関心
を持ちました。
成果とともに課題も提案されており、その課題解決に向かって努力が始まっている
と感じたからです。
お昼寝の時間を使ってミーティングをしている実態をお聞きし、「先生方もご苦労が多いんだな」と思った次第です。
保育者養成とは、"学生"を中心に、
・保育養成の先生
・保育園・幼稚園の先生
・保護者
・行政
が一体となって、主役の「こども」の将来を希望あるものにしているのだなと
思いました。
この一体となってというところが、金城大学短期大学部幼児教育学科の一番
すばらしいところではないかと思います。
いろんな課題はあると思います。だって生の人間に対する仕事なんですから。
でもその分喜びは大きいんだと思います。
このシンポジウムに関係しているみなさんが明るい笑顔で接してくれることが
この仕事に「誇り」をもって当たっている証なんだと感じ尊敬しました。
またの再会を楽しみにしたいと思います。
金城大学短期大学部のみなさん、ありがとうございました。