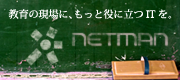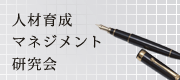2010/07/ 1 (木)
02.学生向けの「働く力」の育成
2010/07/ 1 (木)
コミュニケーション・ラーニングインフラ
"教育"の分野も例外ではなく、もっと"個を生かす"教育に変わっていく必要があると思います。
日本人が得意の"協調"をもっと生かして自立人材を育てていくという視点です。
そのためには、"教室を開く"必要があります。
協働教育のコラボレーションの範囲を広げる価値が高いからです。
そしてそれが可能となるのは、IT技術があるからということです。
どのような教育が可能かは、昨日もこのブログで書きましたので今日は必要なITのインフラとは何かを書きたいと思います。
それは、
「コミュニケーション・ラーニングインフラ」
です。
家庭・学校・地域
親・子・先生
地元・外地域・外国
このようないままで分断されていた三角形が"つながる"ことに新たな価値が創造されます。
なぜ"つながること"ができるのか。
それは、同一の基盤システムを使っているからです。
(教育クラウドというとちょっと薄っぺらくなるかも知れませんが。)
学校の勉強と家庭学習の連動なんてのは一番分かりやすい連携です。
学校では苦手だった部分を家の勉強で補うなんて簡単にできます。
大学でのポートフォリオ(学習履歴)を社会人教育と連動することも可能です。
大学の入試も変わるでしょうし、就職の方法も全く変わるでしょう。
ただ変わる変わるといっても結局
「一人一人が自立して生き抜く力をつける。そのために協調を活用する。」
という教育を再生するということです。
再生というのは、江戸時代の寺子屋に代表されるようにこのような
"人が育つ社会基盤"
が過去にはたくさんあったんだということです。
気骨さを持ちながら柔軟でしなやかな精神。
そんな日本人らしさを取り戻す。
それがITを活用した教育改革なんだと思います。
"自ら学ぶ力をつけるのが教育の本質"
そのための"学びの社会インフラ"を再構築する。
そういった変化が教育にも必要であると、私は考えています。