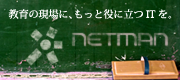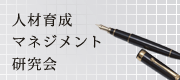2010/06/29 (火)
01.小学生の理科の学力向上
2010/06/29 (火)
ICTを利活用した教育で小学校はどう変わるのか。

情報技術の発達が加速する昨今、"教育"の業界でもICTの活用についての話題が湧き上がっています。
10年以上この分野でNETMANという会社を地道に経営してきた私個人の感情としては、
「やっときたか」という感じです。
今日はICTを活用すると、小学校でどんな授業形式が可能か考察してみましょう。
1.三角形のネットワークが可能
・「子ども」と「先生」と「親」
・「学校」と「家庭」と「地域社会」
・「自分の学校」と「他の地域の学校」と「他の国の学校」
これら3つがつながることにより、単なる情報共有だけでなくコラボレーション(協業)が可能となります。
2.動く教材が可能
・国語:漢字の書き取り順を示す。
・社会:消防署等の役割を映像で見る
・理科:カエル解剖等の実験を映像で確認する。
子どもの興味を引き付け、理解度を向上させることができます。
3.リアルタイムで共有
・小テスト結果を投影し、弱点克服問題を解く
・クラス全体、学校全体、他地域との比較を行なう
等々。
アイデアは尽きることなく出てきます。
結局何が変わるのか。
それは、教室という場が外に向けて開かれる。
ということです。
開かれることによって得るメリットは計り知れません。
いつもと同じ教室、同じクラスメイト、同じ教科書だけを見つめるのではなく、
外と"つながる"ことによって、桁違いの情報を、子供たち自身の目や耳で感じることができる教室。
これが「ソトガク」的な学びの場だと私は考えています。
いつでも誰とでも同時に学べることが、子どもたちの学ぶ心に火をつける。
これが教育の原点として、子供たち自身が学ぶことに対して、ワクワクする気持ちをもつことが一番大事なのではないでしょうか。