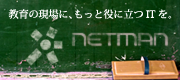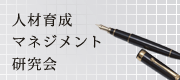2009/10/20 (火)
2009/10/20 (火)
ケータイを活用した授業は、お互いを受け入れる場に変わる
晴れ 気温22度 湿度53% AM6:30 M8189
おはようございます。今日も富士山がバッチリ!見えてます。
ベランダには、山からさわやかな秋の風が吹き込んでいます。
さて
またまた、ネットマンの製品がメディアに取り上げてもらうことができました。
--------------------------
▼ケータイをバリバリに使った授業、その効果は
--------------------------
高校の授業で、ケータイ学習支援ツール(C-Learning)が使われたためです。
公立高校でのケータイ利用ということで、取り上げられやすい面もあるかもしれません。
でも本質は、
「人権教育」
にあることを忘れてはいけません。
それは
・自分と他人の違いを認め、受け入れる
ことからはじまります。
それは、決して、相手に合わせるという”迎合”ではありません。
自分と相容れない相手の意見もあるんだということを認めることです。
違いを受け入れたとき、始めて尊敬の念が沸いてきます。
それが、人権を大切にする態度につながってくるのです。
今回のケータイ活用は、100分授業の最初の6分間で、お互いの意見を
ケータイとプロジェクタを使って公開しあうというものです。
手を上げない生徒も、ケータイなら自分の意見を積極的に話します。
(しかも、あっというまにかなりの量の文字で。。)
100分の授業の最初の6分間、お互いの意見を確認しあうことだけで、
教室という場が、「安心・安全の場」に変わります。
その後の、グループディスカションがどれだけ活性するかは、ご想像のとおりです。
あきらかに、相手をみる目が変わり、意見をぶつけあってもだいじょうぶになります。
ケータイの是非を議論するのは、よいことと思いますし、
依存症とモラルという問題は、情報教育でしっかり対応しなければなりません。
しかし、ぜひ、このような授業現場を見てから、議論してほしいと思います。
幸いにして「ケータイ活用教育研究会」の先生方はオープンです。
いつでも、授業を公開されます。
ぜひお声かけ頂き、見学をしてもらえたらと思います。
きっといい気づきを得られると思いますよ。
さあ上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」