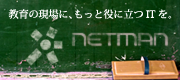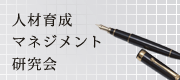2009/08/ 3 (月)
2009/08/ 3 (月)
ケータイ活用の教育の可能性
晴れ 気温26度 湿度78% AM7:00 M8188
おはようございます。今日はきれいな夏の富士山が見えています。
山登りをしている人が見えそうですね。
さて
土曜は信州大学に行き、「ケータイ活用教育研究会」に参加してきました。
東京、大阪、京都などから、松本に40人近い人が、集まって議論しました、
松本城はとってもきれいでした(逆光だけど)
昨年末から始めた、「ケータイ活用教育研究会」は今回で、第6回目を迎えますが、
潮目が変わったなと感じました。先月、大阪で、やったときも30人の先生が集った
とのことです。
本格的な「学習コミュニティー」に発展しそうな雰囲気です。
私は、携帯を使った授業を支援してきて8年になりますが、最近は、外学(外で学ぶ)人が
とっても増えてきただけでなく、先生方の熱気が違います。
学校現場で、ケータイを使わなくてはならない理由があるようです。なぜでしょうか。
キーワードを列挙したいと思います、。
・自己開示
・相互信頼、尊重
・自尊心、誇り
・協調学習
・学生参加
すべて、今の教育の問題点を解決すべきキーワードです。
ただ一番大きいのは、
生徒・学生にとって、ケータイが生活必需品となっている
ことだと思います。
いいも悪いもない。この流れは止まりません。教育現場で、うまくケータイを活用しない、
そっぽ向かれるということでしょう。
授業で使うケータイは、通信機能がついている学習端末です。
(小学5年生が、ゲームの攻略をするのに、自分でYouTubeを検索して
勉強している姿は、そんなに珍しくないでしょう。
子供たちは、すでにDS-iで似たようなことはやっていますので。。)
学習端末としてうまく使えば、教室という狭い空間を、活性させる道具にもなるし、
教室の外とのつながりによって、授業を進めることも可能となります。
また、映像コンテンツの教材を、共有する道具にもなると思います。
座学で行えばいい授業は、eLearning化されていくでしょうから、教室という場
の意味は、”周りに学ぶ”(協調する)ための場所に変化していくと思います。
オフィスという場所も同じですね。パソコンに向かって話さないなら、
家で作業すればいい、もしくはその仕事は誰かに任せればいい。
意見をぶつけ合って、知恵も生むために、オフィスという空間はあるのです。
ケータイを活用する意味・意義が大きく変わったことを示す今回の研究会は、
今後の教育の大きな可能性を感じた会でした。
さあ上げますね。
今日も元気に Let's Chiegumi !!