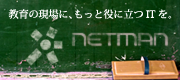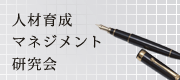2009/05/30 (土)
03.教育へのICT利活用
2009/05/30 (土)
大学教育におけるiPhone×C-Learningの導入。

導入から約半年が経過した今、iPhoneは大学で実際にどのように活用されているのか。携帯電話を授業で活用するノウハウを教員間で共有し、さらなる授業法を調査するために設立された「ケータイ活用教育研究会」の会合で、青山学院大学社会情報学部 助教の伊藤一成氏がiPhoneの活用事例を紹介した。
Act2. "Cラーニング"的、iPhone活用法。

社会情報学部では、iPhone導入以前から、Cラーニングを導入した授業を行っていた。
出欠の確認や教材資料の配付のほか、授業中は学生に携帯電話からアンケートに答えてもらい、リアルタイムで確認できる結果をもとに授業を展開する――といった活用法だ。学生は授業を聞きながら普通に携帯電話を操作し、わきあいあいとした雰囲気だという。
Cラーニングにログインすると、「アンケート」「小テスト」「ドリル」「教材倉庫」などのメニューが並ぶ画面表示される。「相談室」は教員へのホットラインで、ここでメッセージを書くと相手のiPhoneにすぐさま届く仕組みだ。
Act3. "コミュニケーション×ラーニング"の重要性
今回、CラーニングにおけるiPhoneへの対応にあたり、これまでにも増してユーザに「直感的に使える」システムが求められてきていると考える。
とはいえ、システムの発達と比例して伸びなければならないのはコミュニケーションの質である。
Cラーニングのコンセプトは"コミュニケーション・ラーニング"
使いやすく、便利なシステムを使いこなすだけでは、人と人の間に学びは生まれない。
システムは常に人と人をつなぐものとして発展していくべきである、という考えの下、今後もCラーニングが更に教育を支援するツールとして開発していかなければならない。