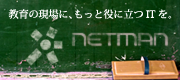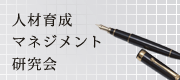2009/04/20 (月)
2009/04/20 (月)
ブレイクスルーの証明
晴れ 気温17度 湿度64% AM6:30 M8187
おはようございます。今日はうっすら富士山が見えています。これくらい見えれば
この時期は最高!。今日もいい仕事ができそうです。
さて
今日からとある大学のゼミと共同研究&授業が始まります。
タイトル
「サービス・サイエンス」を
コミュニケーションの質からアプローチする
サブタイトル
「社会人の学びを極める」
デジタルコミュニケーション ActionT.C.版
学びの共鳴場を分析しよう!
っというものです。デジタル(IT)で行われるコミュニケーションの質を
分析することで、成長にどのように影響しているかを考察すると
いうもの。
3年前から行っている研究で昨年は国際シンポジウムで発表したテーマ
ですが、今年は、大学のゼミ丸ごと(学生20名程度とともに)一緒に
研究していきます。
1年かけてどのような成果発表ができるのか今から楽しみにしています。
2010年2月の情報コミュニケーション学会の大会に発表していきます。
私の仮説は、自己開示とチーム間フィードバックの質を分析できれば、
ブレイク前夜の人を予測することができる
というもの。
昨今、企業では、どうしても短期的な成果が求められ、若者にも早期に
ビジネスマンとして立ち上がることを求めます。
一方で、”遅咲き”という言葉があるように、すべての人が最初から
うまくいくとは限りません。
でも、遅咲きの人が急にブレイクするはずもなく、
・何かしらの思考の深まりがあり、
・その深まりが一旦煮詰まって、壁にぶつかっているときに、
・周りのネットワークとのコミュニケーションによって、パーンってブレイクスルーする
というステップを踏むはずです。
要は、ただ、『うまいくけばいいなー。』『周りとワイガヤ楽しいなー』ってなレベルの
話ではないということです。
ただそれがビジネス現場で語られるほど科学されていない
(認知心理学では大昔から十分研究されているんでしょうが)
ので、どうしても、”遅咲き”より、”早咲き”に着目してしまうんだと思います。
それを、発明した、ActionT.C.のデータを使って分析しようというものが
共同研究の内容です。
今日はその一回目の授業。まずは、彼らにこの研究の意義をしってもらい
かつ、”もっとこうすればいいのではないか。”と議論してもらうことにします。
まずは夏合宿までのイメージが今日の授業で完成できればと思います。
さあ上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」