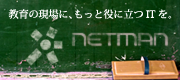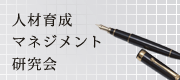2008/11/21 (金)
2008/11/21 (金)
二次会がなぜ本番か
晴れ 気温12度 湿度30% AM7:00 M8186
おはようございます。今日もすばらしい富士山が見えています。しかし寒いですね。
でも昨日、新幹線にジャンパー忘れちゃって、今日はガマンして歩きます。
コメントありがとうございます。こちらでFBします。
昨日、行なわれたNetman主催の「経営理念の勉強会」で、
プレゼンターが、こんなことをおっしゃっていました。
---------------------------------------------
「Help each other(お互いを支援し合う)」 が大切だし大好きだ。
それは、
1.課題(悩み)を共有し
2.課題についてディスカッションし
3.課題を解決していく(勇気とアイデアをもらう)
のステップを踏む。
---------------------------------------------
このような場を作り出す人をスティムレーター(刺激を作り出す人)
というそうです。
ファシリテーターとはひと味もふた味も違う意味ですね。
「学び合いの場」を作るうえで学習環境デザイナーと
して必要な能力は、スティムレーターだと思いました。
1.お互いに言い合える関係を作り出し、
2.お互いの考えをぶつかり合えさせ、
3.新しい知恵を生み出していく。
まさに、私が作り出したい”学び合う場”だと思いました。
私たちは、一次会(勉強会)のあと二次会(懇親会)を必ず
セットします。その価値を説明するのが、わかりやすくなりました。
要は、1.が必要になるので、二次会(懇親会)が重要なんですよね。
単なる一方的な勉強会で、生まれるものは、限られています。
むしろ本を読んだほうが、時間的ロスを考えれば、ましかもしれません。
一方で、参加者同士の学び合いには、大きな知恵が生まれます。
よって、お互いを良く知り合う、感情移入する関係になるには、
気楽な話も含めて、相手がどんな人かわからなければなりません。
それが二次会というものですね。
要は「二次会が本番」といういい方より、「二次会から始まる」
といった言い方のほうが正しいということですね。
勉強会(一次会)は二次会の話しを共有化するための
時間なんだということです。
そしてキッカケや接着剤の役割になっているのが、スティムレーター
たる、勉強会を取りしきる人なんでしょう。
どうでしょうか。
だんだん、「学び合う場」の表現の仕方が、シンプルになり分かりやすくなります。
どんどん知恵が生み出されていきますね。
さあ上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」