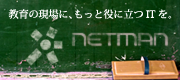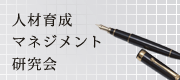2008/10/31 (金)
2008/10/31 (金)
コミュニティーを活性させる
晴れ 気温18度 湿度60% AM7:40 M7985
おはようございます。今日も雲で富士山は見えませんでした。
残念。変わりに石垣のマングローブの木をお楽しみ下さい。
今日は学習環境の中心である、実践共同体(コミュニティー)について
考察してみたいと思います。
家族もコミュニティーです。
地域もコミュニティーです。
組織もコミュニティーです。
サークルもコミュニティーです。
でも、活性しているコミュニティーと停滞しているコミュニティー
があります。
情緒的にならないように、活性と停滞を定義しましょう。
活性とは、
「コミュニティーの構成員(メンバー)全員が、積極的に自分から
関与している状態。新参者も、当初少しの関わりながら、中心的な
役割を担うまでの期間がとても短く、早めになじむ状態。
雰囲気は、みな楽しそうで、輝いてみえる。」
停滞
「一部の人間しか積極的関与をしておらず、受身のメンバーが多い
状態。新参者は、なじみにくく、排除されやすい。
雰囲気は、苦しそうで、無理している感じにみえる」
コミュニティーが学び合いの場(学習環境)になっている状態
とは、活性している状態ですね。というより、むしろ、”学習する”
ということ自体が、メンバーが積極的に関与していくプロセスそのもの
であり、結果として得るものではないんだ。ということです。
-------------------引用開始------------------------------------
正統的周辺参加(LPP: Legitimate Peripheral Participation)
「学習は人が実践共同体に参加すること
-当初は周辺的参加から,次第に十全的参加へ-
を通して共同体としてのアイデンティティを確立していく過程である」
(佐伯胖)
佐伯胖監修,『学びとコンピュータ ハンドブック』,CIEC編,東京電機大学出版局,2008年8月1日.
ジーン・レイヴ,エティエンヌ・ウェンガー,『状況に埋め込まれた学習(正統的周辺参加)』,佐伯胖訳,産業図書,1993年.
-------------------引用終了------------------------------------
ではどうやったら”活性”した状態がデザインできるのでしょう。
メンバーから見た主語で整理しましょう。
1.コミュニティーが目指している姿に共感する。
2.コミュニティーに参加する。
3.情報を受け取るだけなど、少しだけ関与する。
4.自分の意見を発信し、受け入れられ、楽しくなる。
5.役割を自分で見つける。
6.プロジェクトを起こし、一部でなく、主役として活躍する。
7.新しい仲間をどんどん誘う。
8.新しい仲間を積極的な活動が出来るよう支援する。
すべてのメンバーが、1から8までの経験をするコミュニティーが、
とても活性しているといえるでしょう。
学習環境デザイナーとしては、この1から8をデザインできなければ
ならないということになります。
まず、自分がメンバーとして、1から8を体験する必要があると思います。
自分が、思い入れがあれば、コミュニティーを”学び合いの共同体”にする
熱意が生まれてきます。
この人たちを”つなげていきたい”というモチベーションにつながると
思うからです。
どうでしょうか。あなたも学習環境デザイナーになりませんか?
なりたい人は、楽しくてしょうがないと思うんで、どんどん始めましょう!
では上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」