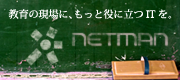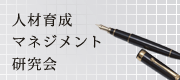2008/09/10 (水)
2008/09/10 (水)
学習環境デザイナー
晴れ 気温24度 湿度59% AM7:20 M7883
おはようございます。今日は雲1つなく、すばらしい富士山が見えてます。
いつもより大きめに乗せますね。ご覧下さい。
---------------
【今日の仕事】
今日は東京で会議をしたあと、I-Villageにて役員会があります。
-------------
【昨日のブログコメント】
みなさん、コメントありがとうございます。なかなか気づきが多いコメントが多かったです。
フィードバックにも時間が掛かりました。
まさにコメントも気づきを与えてくれる(成長させてくれるもの)ですね。
こちらにまとめてフィードバックしています。 いろんな人の意見も面白いですよ。ぜひお読みくだい。
-------------
今日の文章は、
「佐伯胖監修 CIEC編 学びとコンピュータハンドブック」
から得られた情報で書かれています。
昨日
「教える中心から、学び中心へ」
と書きました。
これは、人材育成に社会構成主義(ヴィゴツキー)を取り入れる
ことを指します。
もちろん、これからも、行動主義、認知主義も重要ですが、
共同体での学びをどのようにデザインするかを考えることが、より重要です。
”教える”は、”教授法”が問題になります。
一方”学び”は、”学習環境”が問題になります。
”教える”だと、外発的動機付け、内発的動機付けを仕組けとして取り入れますが、
限界が見えてきました。
”学び”の、共同性のデザインを取り入れる必要があります。
ネットマンに肩書きをつけるとしたらなんでしょう。
「ITを活用した学習環境デザイン」のネットマン
です。
では、私たちの肩書きを1つつけるとしたら何でしょう。
それは
「学習環境デザイナー」
となります。
私たちは実は昔から、ICTを活用して、どのような学びの環境を
作り出すことができるかをデザインしているのです。
(Network-erモデルがそうだから、仕事も自然にそうなります。)
前述の本では、「学習環境デザイン」とは、
・活動のデザイン
・空間のデザイン
・共同体のデザイン
をデザインすることと書かれています。
・活動のデザインでは、
学習者にとって、目標が明快であること
新しい知が生み出されるなど、活動自体がおもしろいこと
苦しいと面白いという矛盾の感情が共存していること
をデザイン。
・空間のデザインでは、
参加者全員にとって居心地のいい場所であること
学習に必要な情報や道具が手に入ること
仲間とのコミュニケーションが簡単で自然発生的であること
をデザイン。
・共同体のデザインでは、
目標を常に共有したり、新しい仲間がライブラリーで昔
を学べるようにしたり
をデザイン。
そしていつでも、実践しながら考え、モニタリングして評価
しながら、デザインを改良し続けることを行う。
これが、「学習環境デザイン」だそうです。
どうでしょうか。
そうなんです。まさに、今まで私たちが仕事で行なっていることばかり
が書かれています。
そうなんです。私たちは
「学習環境デザイナー」
だったんです。
へっー。そうなんだー。
今頃ぉー。気づいたのかよー。
と突っ込みがありそうですが、どうぞ気軽に突っ込んでください。
かなりの実績を積み上げた後に、
私たちはこうだった。
と気づいたほうが、カッコいいですよね。
現場の問題を解決し続けた、口だけのウンチク屋ではない、
汗くさい仕事をしてきた私たちだから言える言葉です。
どうでしょうか。
共通の価値観の発信が出来上がっていくでしょうか。
さあ新横浜を過ぎそうです。上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」