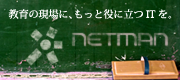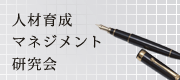2008/08/ 1 (金)
2008/08/ 1 (金)
行動主義に立たない研修
曇り 気温27度 湿度74% AM7:30 M7884
おはようございます。今日は雲りって富士山は見えません。家庭菜園に
果物という手があることに気がつきました。キウイ、ブドウ、イチゴ、ブルーベリー
どれにしましょうかね。
さて今日はe-LearningWorldに参加しているとある会社の社長と商談のため
東京ビックサイトに行きます。アポはありませんので、突撃ですね。
-------------------------
さて”研修”は果たして何の為にあるんでしょうか。
私は、
”ゴール目標を同じくする仲間の
個々の行動目標を達成するための
行動実践コミュニティー作り”
と言い切っていますが、
そもそも”行動目標”がハッキリしない研修がありえるのです。
昨日、”行動定着型研修セミナー"が行なわれましたが、
その中で、O社のMさんの談話です。
「新任の管理職研修など、いろんな部署の人が集まって、
1つのテーマで話し合う自体が意味のあるものがあります。
会社としては、そこに”会社のテーマ”を入れ込むんですが、
それが、本人にとっては、モチベーションを上げるものとは
限りません。その逆になる場合もあります。
しかし意味のないことかと言えば、そうではなく、すべての
年齢の人がとある階層になったときに必ず行なわれる研修は、
続けることに、非常に意味があります。
長期的に効果を見る必要があるんです。」
学びの考え方には
1.行動主義(行動変容が成果。ハッキリ見て分かる)
2.認知主義(心の中の認知の広がりが成果。)
3.構成主義(周りとの係わり合いの広がりや太さが成果)
の3種類があります。
1.の行動主義に立った場合、
”個々の行動目標”を達成することが目的になりますが、
このO社のMさんの話は、
2.の認知主知、3の構成主義に立っていると言えます。
特に、”あつまって他の部署の人と話すことに意味がある。”
と言うことは、3.構成主義ということです。
もちろん、
「あのときあんな話をしたよね。ちょうど××部門の人と同じ
グループだったんですよね。」
といった長期的な目線もあると思いますが、
短期的にも社内のネットワークが広がり、本音で話し合う同期(管理職)が
増えるという、効果があるわけです。
ならば効果を計測することは可能と私は思います。
なぜなら、社内ネットワークは、3.構成主義のことですし
本音で話し合う、は、2.認知主義の認知が広がらないと人と話せないからです。
もちろん彼らの評価を目的にした計測なぞ、意味がありません。
でも、経営者にしっかり”説明でき、”人材開発”に関して”コスト”から”投資”という
考え方にチェンジさせるためには、しっかりした、効果測定が必要と思います。
よって、効果を求めない”研修”というものはないわけで、どんな研修であっても、
ねらいどおりパフォーマンスを発揮したのかということを計測する必要があると考えます。
注意点としては、単なるLevel.1)の満足調査だけ行なっても、価値がないということです。
現場に戻った後の効果を考えたとき、満足したものがいいとは限らないからです。
どうでしょうか。
あなたの”研修”は何を効果として考えていますか?それは研修後、どれくらいでの
効果ですか?
さあ上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」