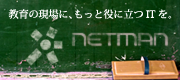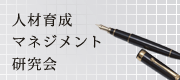2008/06/19 (木)
2008/06/19 (木)
C-Learningコンセプト
曇り 気温23度 湿度79% AM7:30 M7884
おはようございます。今日も曇っていますので、予告どおり、トマトをお送りします。
いったんもぎとられなくなった実がやっと復活してきましたよ。
さて今日の午前はI-VillageでATCの計測系システムのミーティング、午後は、C-Learning
の新レビジョンのミーティング、夕方に東京で、とある企業同士のコラボ研修のミーティング
があります。
昨日はとある大学で、
「教育環境とメディア」
の特別講義を行ってきました。
25人程度の学生が参加していました。
授業では、大学教育がケイタイを利用することでどのように変化
していくか(いかせるか)を話しました。
C-Learningは
Communication Learning
<多人数講義で、学生が参加する授業>
↓
Collaboration Learning
<大学を超えて、学生が参加する授業>
↓
Community Learning
<学生同士が、学びあって成長する場>
という成長を遂げる話をしました。
最後に、
「今日の授業での気づきや学びを答えてください」
というアンケート回答では、
・学生にとっても教師にとってもメリットがある。
通信を使うことで、今まで以上に二者間で通心を育むことが出来る。
・時代の流れによって、携帯電話の価値が変化していることにとても驚いた、
今までにない学習方法はとても画期的だと思った。
・単なる授業だけのC-ラーニングしか考えてなかったが、コラボやコミュニティの
発想により、何やら面白そうな事が期待出来そうだ
という「教育方法そのものに対する気づき」があったり
・先生が質問したことについて生徒の色んな案がリアルタイムで聞けて充実していた。
・自分が今まで受け身的に授業と関わっていたことに気付かされた。
・発表しないけど良い意見を持ってる人は沢山いると思うので、その人の意見を
引き出せることが良いと思います。
といった「自分が授業に参加する価値に気づき」がありました。
要はシャに構えていそうな学生も、伝え方によってはしっかり受け止め、
学びを自分で作り上げることができる。ということです。
大学生をもっと大人として温かくも厳しく接し、自立の重要性を説き、
同時に、最新の教授法によって協調学習を促進していくというやり方を
もっと多く取り入れるべきだと思います。
たった4年で社会に出る彼ら。。そこにはグローバルと多様性に対応できる
現状打破型人材が求められます。
グローバル力=英語力でないことぐらい、1年生の4月で気づかせてあげる
べきだと思います。
社会人2年目でそれに気づいても遅いからです。。
”教えられる”、”段取りを整えられる”ことに慣れてしまって、”正解”を
求めてしまう「マニュアル人材」を養成している今の学校教育の転換
を早くやらねばなりませんね。
教えている先生たちは楽ですよ。だって、ずっとこれからも大学という”村”
にいるんですから。ある意味、人材育成の結果責任は問われません。
でも輩出される学生はたまったものではありません。
その”村”の価値観とは、まったく違う価値観の場所に行くんですから。
もっとC-Learningのコンセプト(ITではなくて教育方法としての思い)を
もっと発表していかなくてはいけないと昨日は学生たちに教えられました。
『みんな、ありがとう』
では上げますね。
今日も元気に「いってらっしゃーい」