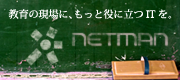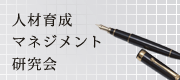2007/12/10 (月)
2007/12/10 (月)
新学習指導要領で変わるか
曇り 気温10度 湿度40% AM6:50 M7782
おはようございます。今日は曇っていて富士山は見えません。
最近朝晩の冷え込みが和らぎ暖かくなりましたね。
さて今日は朝会社によった後、一日京都です。
とある企業に”文化育成”のソリューションを説明した
あととある高校に行き、情報の授業の仕方について話し合います。
この土曜はとある学会に参加してパネルを行ったきました。
基調講演で来ていた国の審議官と話す機会が多くあったり、
東京で新しい教育系の団体を設立されようとしている教授
に会ったりととても楽しい時を過ごしました。
審議官の方には、新春に制定される学習指導要領について
私なりの考えを述べさせて頂きました。
「この教科は”人づくり”の教科であります」
という話に感動したのに、中身が私にはテクニカル過ぎるように
感じたからです。
よく耳を傾けて頂き、もっと現場の話を聞きたいとおっしゃって
いて、会の後もいろんな方と議論していましたので安心しました。
その教科については、いい指導要領ができあがるでしょう。
小学校から変える話をしていましたので、期待できますよ。
でも本当の課題は”現場”にあることは変わりません。
先生同士の交流が圧倒的にたりないな。と感じました。
会があった件では、300人の先生がその科目を受け持って
いるとのことですが、30人程度の先生が来ていただけ。
積極的に外の先生と協力し、”教授法の技術”を高めよう
としている先生は、まだ少数でした。
教育って場当たり的な活動になりやすいですね。
目の前の問題に対処し続けなければならないですから。
教育って保守型の先生が多いですね。
だって身分が保証されていますから。
休み時間にとある女性の先生が、
「○○についてはいつも生徒に教わっているんです」
と言っていました。
いいじゃないですか。彼らの方が良く知っているんですから。
その代わり
「先生は□□を良く知っているから教えましょう」
というアプローチもあると思います。
場面によっては生徒と先生を逆転させてしまうという発想
です。人生の師である先生にはもっとたくさん学べる場所
があるんですから、狭い範囲で拘ってもしょうがないですよね
へたに権限を使うと、生徒はほっておくとどんどん裏へ裏へ行って
しまいます。学校に隠れた世界をたくさん作るだけです。
受験勉強は塾で十分って話になってしまいます。
ほんとやっかいな状況ですね。なんか別のスキーム作らないと
脱出できないかもしれません。
今の学校がもっとオープンになり、教授の技術をプロとして
高め合い、学び合う場所がもっとないといけない感じは持ち
ました。
学会などで知識や実績の発表しあいと懇親だけでは、プロ
としての技術は高まらないですから。。お友達は増えても。。汗
さあ東京に着きました。すぐ下りの新幹線に乗るんですけど。。
では今日も元気に「いってらっしゃーい」