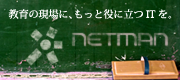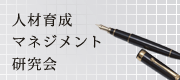2007/11/ 6 (火)
2007/11/ 6 (火)
教育ベンダーとHRD担当者の関係
曇り 気温18度 湿度67% AM7:10 M7782
おはようございます。厚めの雲におおわれている富士山です。山には霧がたちこめ
幻想的な雰囲気をかもしだしています。こんな雰囲気も山と海の近くに住んでいる
から見れるんでしょうね。
今日の予定はHRDMの理事とのミーティング、午後はPKGビジネス
のミーティングです。合間でHRDMの案内パンフ、Homepage
に使うライティングをやっちゃおうと思います。
さて
今日は教育ベンダーのことを書きましょう。
いわゆる研修屋さんのことで、企業の人材開発部門と
ともに社員教育を担っています。
○○ラーニングという名前や独自色とあるユニークな名前の
企業が多く、大きくメーカー系列の子会社の場合と、独立系
の場合の2種類があります。
発注するのは、企業のHRD部門のことが多いので、その2社
(というか2人)は非常に濃厚な関係になることが多いです。
営業的にも親会社があったり、蜜月の関係があったりするので
一度、関係をもつと長くつき合うことになり、随時契約が多く
なります。
研修企画担当者がベンダーに
「去年と同じやつで。」
なんて会話は、競争市場でないベタベタな世界であることを
如実に語っています。
そんな中でいい学習って生まれるんでしょうか?
中には努力しているベンダーやHRD人材育成部門の人は
多くいますが、なんか研修を回すことで一生懸命になっており
育成って視点、結果責任を追っていないような気がします。
蜜月が進みすぎると、効果のない研修をいかにも効果のあるよう
にアピールしあうHRD担当とベンダーって構図ができあがります。
怖いことです。選択する人に間違った情報がわたりますので。
これは賞味期限の改ざんが相次いでいる食品業界と同じ
ことが起きているのと同じです。
やはり教育効果測定手法の標準化が必要です。
そして誰でも簡単でスグ実践できなければ意味ありません。
実践で品質定義がバラバラになってもしょうがないですから。
要は効果測定そのものに品質保証が必要なんです。
誰がやっても同じであり、それが広く一般化するのが簡単である
ことが条件です。
結論、標準ツールを早急に広める必要があります。
現場で日々起きていることを真剣に体験すれば、
教育改革は待ったなしであることはスグわかると思います。
ゆっくりHRDの連中のお勉強を待ってはいられません。
新しいスキームを考えなければならない季節がやってきた感
があります。
だれかが旗振りをやらねばならんでしょうね。
HRD業界からはこの改革の船は出航しないでしょうから。
さあ東京に着きました。上げますね。
では今日も元気に「いってらっしゃーい」