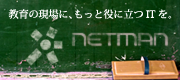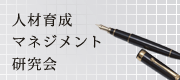2006/12/18 (月)
2006/12/18 (月)
教育基本法に「学習」は3つ
晴れ 気温6度 湿度43% AM6:30撮影
おはようございます。今日もいい写真が取れましたよ。月曜の朝なので、富士山を
しばらく眺め、『ふっ~。』と息を吸い込むと、とても清々しい気分になります。
さて
今日は午前中は、全社員参加の朝定例。午後は、アライアンスパートナーとのミーティング
に出向いたのち、会社にもどり、「きくすけポータル」の新業務システムについての報告を
受けます
ところで、教育基本法が改正されましたね。
新しい基本法に「学(習)」という文字数が何個出てくるか数えてみました。
第3条(生涯学習の理念) ・・・あらゆる場所において学習することができ、・・・
第6条(学校教育)・・・自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視・・・
第10条(家庭教育)・・・保護者に対する学習の機会・・・
3つありましたね。
先週の、土曜日に青山学院大学のeラーニング人材育成研究センター(eLPCO)
で講演をしてきましたが、そのセンター長の言葉に、
「・・・様々な教育内容の固有の問題を理解し、学習者の「学び」を真に支える
学習環境をデザインできる・・・・」
とあります。
まさに、「教える」から「学ぶ」 という発想の転換
そして、「教育のデザイン」から「学習のデザイン」 への転換
が求められてくるということですね。
もっと分かりやすくいいましょう。
「教える」から「教えない」という転換です。
教えないで、人材を育成するにはどうしたらよいのでしょう。
そこに「自律・協調学習」や「学習する組織」の考えがとても大事になっていきます。
学校教育に必要なのは、チーム学習と学年という考えをなくすことでしょうか。
企業文化に必要なのは、お互いに本音でフィードバックし合える文化でしょうか。
いずれも多様な考えをももった人同士がぶつかり合うとき、知恵や学びが生まれること
がベースの考えにいなっています。
ここには、教える人は必要ありませんね。学びを設計するデザイナーと、
ファシリテーターのような役割が必要となってきます。
1人1人のらしさを大事にしながら、周りとコラボレーションして、ものを生み出す力ですね。
この国はどう変わっていくでしょうか。。
さあスタンダップが始まったようです
では今日も元気に「いってらっしゃーい」